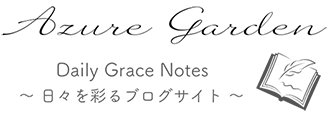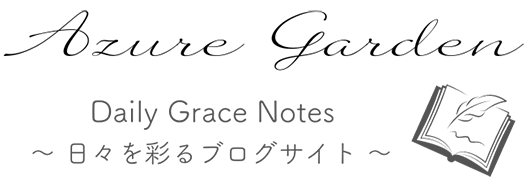【植物に学ぶ琉球文化】つる性植物の女王クレマチスと琉球王国
/ Last updated: 2025.10.29

今日は文化の日ですね。
文化の日が近づくたびに思い出すのが、故郷・沖縄の首里城が2019年10月31日未明に焼失した、あの「衝撃的」な出来事です。
あれから、もう4年。
帰省のたびに首里城に足を運び、復興の様子を見守っています。
この時期、首里の町では「首里文化祭」が開催されます。今年は「首里城復興祭」として、4年ぶりに再開されるとのこと。
最大の見どころは、かつての琉球王朝時代を再現した「古式行列」。国王が国家の安寧と五穀豊穣を祈願した祭礼を模したもので、「琉球絵巻行列」として親しまれています。
そんな文化の日に、ふと王朝時代に思いを馳せて首里城のことを調べていたところ、琉球王国とイングリッシュガーデンでおなじみのクレマチスとの、意外な繋がりを発見しました。
今回はそのお話をお届けします。
クレマチスと琉球王朝の意外な関係
クレマチスといえば、イングリッシュガーデンには欠かせない、バラのコンパニオンプランツのひとつ。
「つる性植物の女王」とも称され、つるバラと組み合わせて、美しい庭園の風景を生み出します。
イギリスでは、王室メンバーの名前を冠した品種も多く、国民に深く愛されています。
そんな華やかなイメージのクレマチスが、かつて琉球王の玉座にも描かれていたというのは、驚きでした。

イングリッシュガーデンのクレマチスとつるバラ(Clematis and Rose)
クレマチスの特徴
クレマチスは、キンポウゲ科クレマチス属の総称です。中国から日本に伝わった花で、現地では「鉄線蓮(テッセンレン)」、「鉄線葛(テッセンカズラ)」などと呼ばれています。その名前は、クレマチスのつるが非常に堅いことから来ています。日本では、「鉄線(テッセン)」と呼ばれています。

ハリのある堅いつるから鉄線(テッセン)と呼ばれた
テッセン(鉄線)の持つ意味
堅くしなやかなつるを持つテッセンは、「強い結びつき」の象徴。
日本の着物の文様にもよく登場し、「夫婦円満」「恋愛成就」を表す縁起の良い花として、婚礼衣装にも用いられてきました。

和柄のテッセンの花
出典: okuni / Adobe Stock
琉球文化とクレマチスの結びつき
琉球文化は、古くから海外との外交が盛んでした。
その中でクレマチスは、紅型などの伝統工芸品のモチーフとしても取り入れられていたことがわかっています。
実は、かつての首里城正殿の御差床(うさすか)──王様の玉座──にも、クレマチスが描かれていたそうです。
(※2019年10月に焼失)

首里城 正殿二階 御差床(うさすか)
出典: mtaira / Adobe Stock

首里城 正殿二階 御差床のクレマチス
————— —————
首里城公園の公式サイトによると、江戸時代、日本本土で花模様が着物や工芸のデザインとして流行し、その影響が琉球王国にも及んだのだとか。テッセンの文様もそのひとつとされています。

「イングリッシュガーデンで見たクレマチスの花」と「琉球王の玉座の文様」
————— —————
以前、イングリッシュガーデンで撮影したクレマチスの写真と、玉座の文様を並べて見比べてみると──堅い針金のようなつるの描写が丁寧に再現されており、両者に確かな共通点を感じました。
外交に長けた琉球王国。
その王の玉座にクレマチスの文様が取り入れられたのは、来賓に対し「堅く深い絆を願う」という思いが込められていたからではないか──そんな想像が膨らみます。
また、星のような形で咲く花には、「両国の繁栄を祈る」という願いも込められていたのかもしれません。
おわりに
沖縄の伝統工芸には、「沖縄には実在しないもの」をあえてモチーフとした作品が多く存在します。
それは、外交から得た“異国への憧れ”が、琉球独自の技法によって形となり、今に伝えられている証でもあります。
これからも、私たちの周囲にある豊かな自然の中で見つけた発見を、共有していきたいと思います。

参考:正殿玉座に描かれた花 クレマチスのお話, 首里城公園公式サイト
※この記事は、関連サイト「Azure Garden」の自然を楽しむブログより移行・再編集したものです。(2025.8.14)