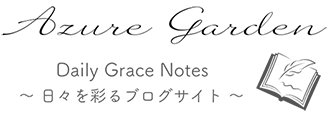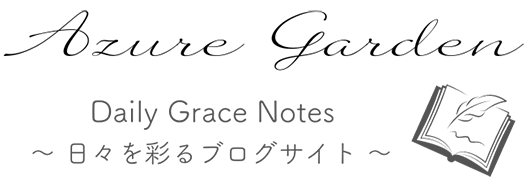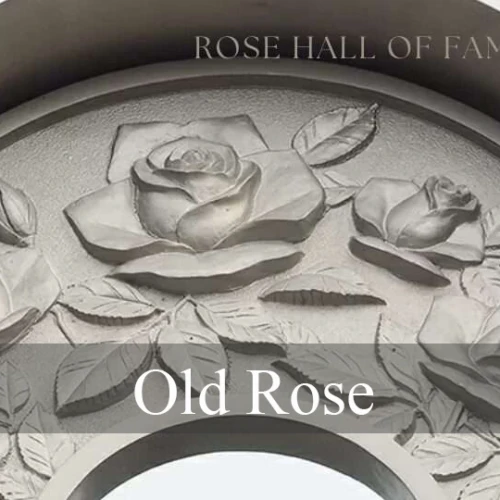春を彩る桜の種類|日本の野生種と栽培品種の魅力
/ Last updated: 2025.11.05

もうすぐ桜の季節がやってきます。
毎年のことですが、桜の季節に散歩していると、見ず知らずの人たちとも自然と「桜が綺麗ですね」という言葉が交わされます。この季節には、桜の美しさに心が和み、誰もが笑顔になるような気がします。
そんな温かく、明るい気持ちを感じる春の訪れにちなんで、私が身近で出会った美しい桜たちを紹介したいと思います。
大島桜(オオシマザクラ)のような野生の桜から、染井吉野(ソメイヨシノ)や河津桜(カワヅザクラ)のような栽培品種に至るまで、それぞれの桜が持つユニークな特徴や意外な関係性についてご紹介します。
Contents
桜の野生種
野生種とは、山や野など自然の中に昔から自生している桜のことを指します。
人の手が加えられず、自然のままの環境で育っているのが特徴です。
現在見られる多くの栽培品種は、こうした野生種をもとに交配や品種改良によって生まれています。
ヤマザクラ(山桜)
日本在来の野生桜「ヤマザクラ」。古くから人びとに親しまれ、その姿は幾つもの和歌に、日本の心として詠まれてきました。

エドヒガン(江戸彼岸)
山地の斜面などに自生する長寿の桜で、樹齢1,000年を超える古木も見られます。ソメイヨシノの交配親としても知られています。

オオシマザクラ(大島桜)
伊豆諸島や伊豆半島に自生する桜で、純白の花とすっきりした香りが特徴です。葉も早くから展開し、桜餅の葉として使われることでも知られています。
鮮やかな濃い紅色の花が特徴の早咲き種。沖縄や台湾でも見られ、釣り鐘状の花がうつむき加減に咲く姿が印象的です。

この他には、オオヤマザクラ(大山桜)、マメザクラ(豆桜)などがあります。
————— —————
カンヒザクラ(寒緋桜)
カンヒザクラ(寒緋桜)は、国外から持ち込まれたものと考えられているようで、もともと国内に自生していたかは不明のようです。
オオシマザクラ同様、栽培品種の交配親として利用されています。
クメノサクラ(久米の桜)
こちらは、私の地元沖縄で見られる”ソメイヨシノに似た”「久米の桜(クメノサクラ)」。久米島に自生する桜で、沖縄本島内でもクメノサクラを広げる動きが年々高まっているようです。

桜の栽培品種
栽培品種とは、人の手によって生み出された桜のことを指します。
現在も、さまざまな新しい桜が育種・開発されています。


カワヅザクラ(河津桜)
静岡県河津町で発見された早咲きの桜。鮮やかなピンク色と開花の早さで、春の訪れをひと足早く告げてくれる存在です。

ソメイヨシノ(染井吉野)
日本で最も広く親しまれている桜。淡いピンクの花が一斉に咲き、満開の風景はまさに春の象徴です。オオシマザクラとエドヒガンの交配種とされています。

シダレザクラ(枝垂れ桜)
しだれるように枝を垂らして咲く優雅な姿が魅力。エドヒガン系が多く、古木や名所も多く残されています。

カンザン(関山)
八重咲きの桜の代表格で、花びらの多さと濃い紅色が特徴です。遅咲きのため、春の終盤まで花見が楽しめます。

————— —————
ジンダイアケボノ(神代曙)
ワシントンに贈られたことで知られるアケボノザクラに近い系統で、神代植物公園で選抜された栽培品種です。
淡紅色の花が可憐に咲き、病気にも強いことから注目されています。
そして今では、ソメイヨシノに代わる「次世代の桜」として期待されている品種でもあります。

————— —————
私がこれまでに出会った桜たちをご紹介しました。
同じ「桜」でも、咲き方や色、たたずまいはそれぞれに個性があります。
ふと足を止めた先で見上げた桜が、少しだけ違って見えてきたら嬉しいです。
※この記事は、関連サイト「Azure Garden」の自然を楽しむブログより移行・再編集したものです。
————— —————