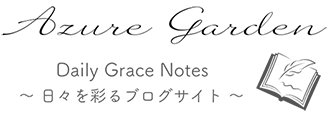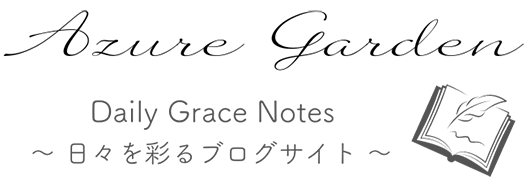沖縄のスーサーと出会う 〜 イソヒヨドリのフォトダイアリー
/ Last updated: 2026.02.03

可愛いポーズをとるのは イソヒヨドリ。
地元・沖縄では「スーサー」と呼ばれ、首里城周辺や道端でも ちょこちょこ歩いている姿をよく見かけます。
2、3年前から写真を撮ろうとしていましたが、なかなかタイミングが合わず、上手く撮れなかったり、カメラを持っていなかったり…。
今回は、ようやくこんな近くで撮ることができました♪
イソヒヨドリの特徴
イソヒヨドリの特徴は、オスとメスで羽の色が大きく異なります。
オスはくすんだアッシュブルーの羽に落ち着いたレンガ色のお腹が特徴で、遠目にも美しく映えます。
一方、メスは全体的に地味な茶色や灰褐色で、模様も細かい斑模様が入るため、周囲に溶け込むような色合いをしています。
そのため、イソヒヨドリと気づかずに見過ごしてしまうこともあります。
体長は約23cmほど。スズメ(約14cm)よりひと回り大きく、ハト(約33cm)よりは小さいサイズ感です。

イソヒヨドリ(Blue rock thrush) 沖縄県本部 2025.3.3
イソヒヨドリの魅力
青い鳥で知られるカワセミやルリビタキなどとは違い、イソヒヨドリのくすみブルーは控えめな美しさを感じさせます。

イソヒヨドリ(Blue rock thrush)
カワセミがコバルトブルーの「空飛ぶ宝石」なら、イソヒヨドリは、デニムに革のバッグを合わせたような、味わい深いヴィンテージブルー。
海辺の鳥なのに近年は内陸でも繁殖
イソヒヨドリは、その名前が示すとおり、もともとは海岸や岩場に生息する鳥です。
「磯にいるヒヨドリのような鳥」として名付けられていますが、実際にはヒヨドリの仲間ではなく、ツグミの仲間に分類されます。
英語では Blue Rock Thrush(青い岩ツグミ) と呼ばれ、その名のとおりツグミの特徴を持っています。
しかし近年では、内陸部や都市部にも進出し、東京のような都会でも繁殖が確認されています。
なぜ都市環境に適応しはじめたのか、その動向はまだ解明されていない部分も多いようです。

イソヒヨドリ(Blue rock thrush)沖縄県那覇市 首里城近くにて 2025.3.7
今回の帰省中、オスは何度か見かけたものの、メスには出会えずにいました。
帰る間際、ふと庭の塀に目をやると、一羽の鳥がとまっていました。
スズメより大きく、ハトほどの丸みもない。茶褐色の羽——きっとイソヒヨドリのメスだったのだと思います。
慌ててカメラを取りに戻りましたが、戻ったときにはもう姿はなくなっていました。
今回はカメラに収めることはできませんでしたが、また次に出会えるのを楽しみにしたいと思います。
参考:「海辺の鳥」なぜ内陸部へ イソヒヨドリの謎を追って〈2023年10月15日号〉, 東京民放 WEB週間新聞 東京が見える!東京を変える!, 2025.3.5

———- ———-
————— —————
・身近で見られる野鳥たちはこちら。
————— —————
野鳥の美しい瞬間を、より鮮明に。
高速AFと優れた手ぶれ補正を備えた【OM SYSTEM OMDシリーズ】なら、遠くの被写体もくっきり撮影。
軽量ボディで持ち運びも快適です。

![]()
詳しくはこちら -> OM SYSTEM STORE
![]()